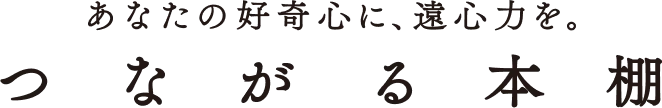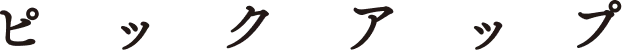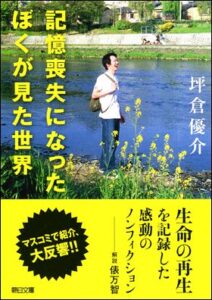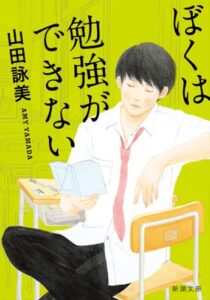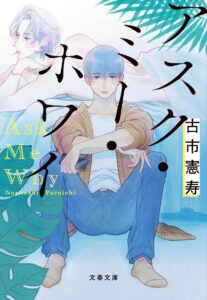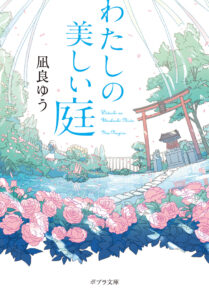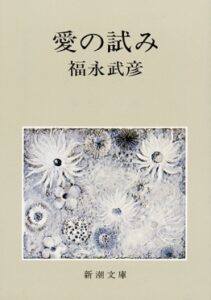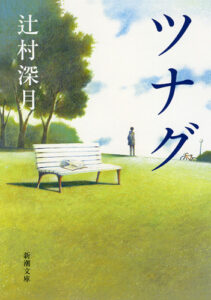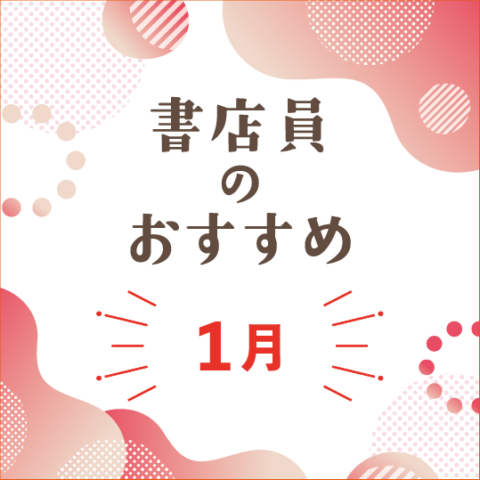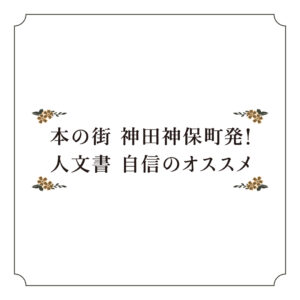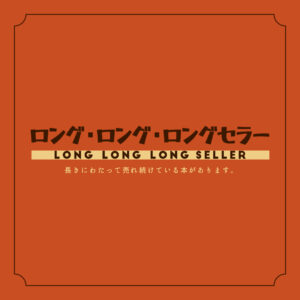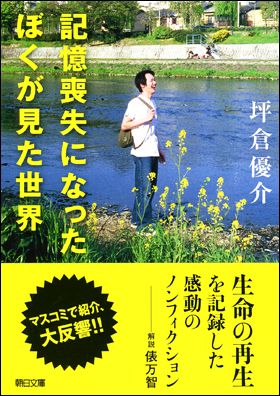
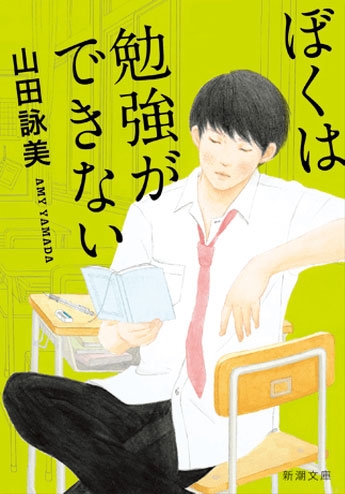
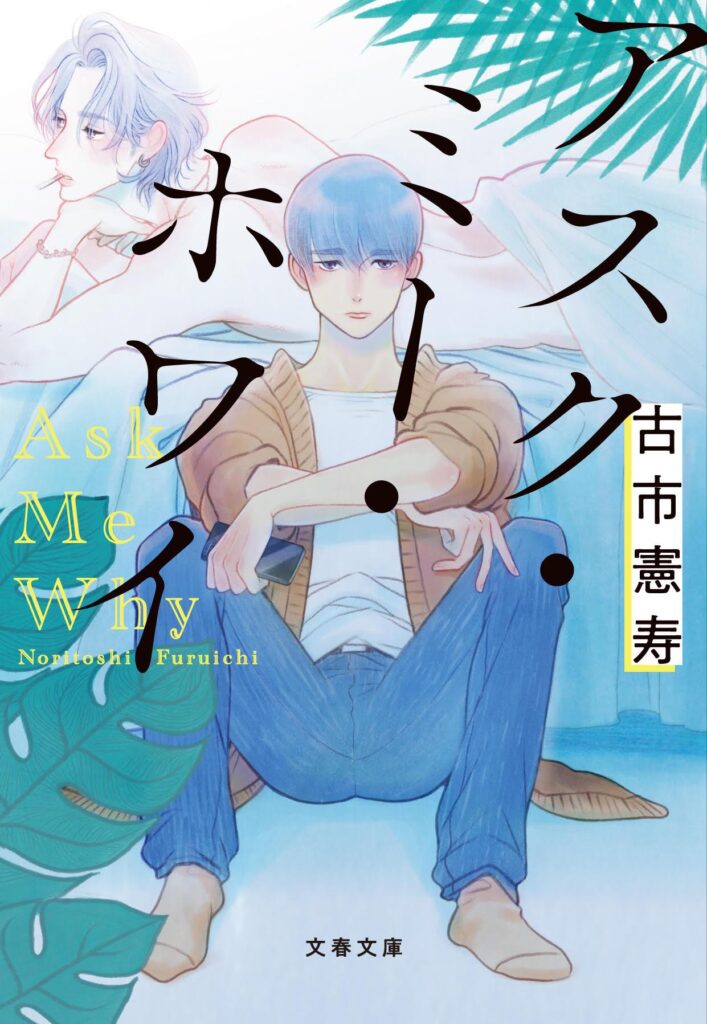
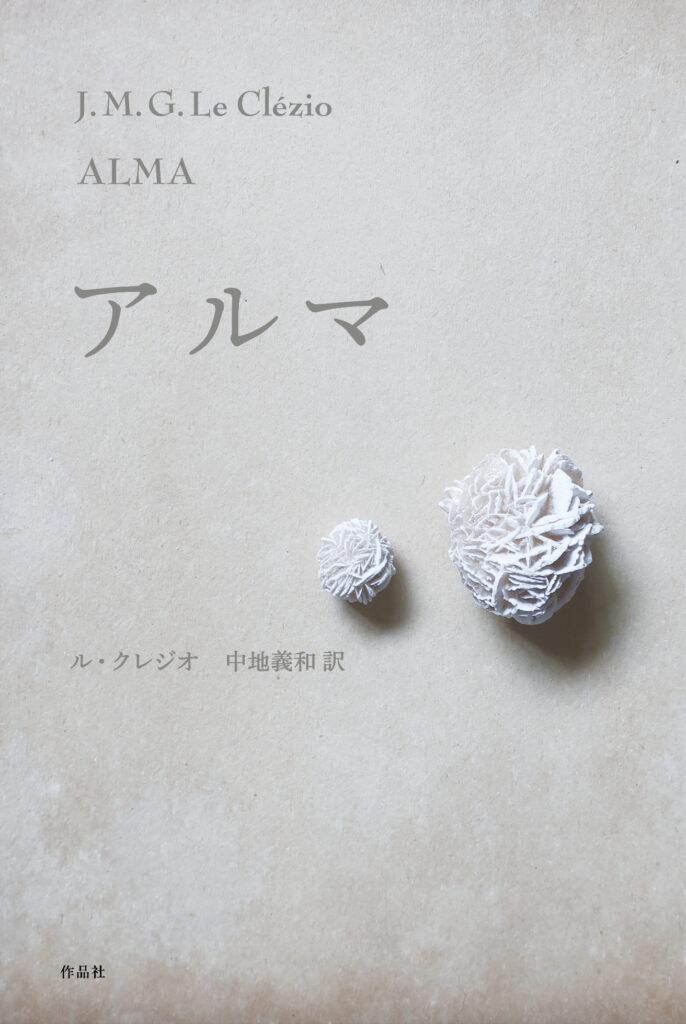

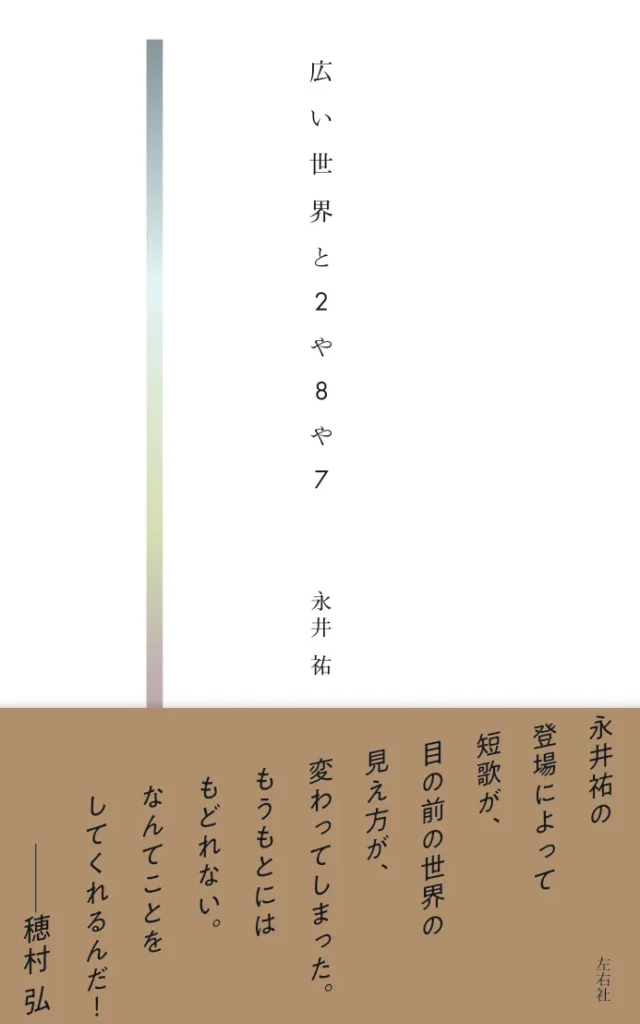
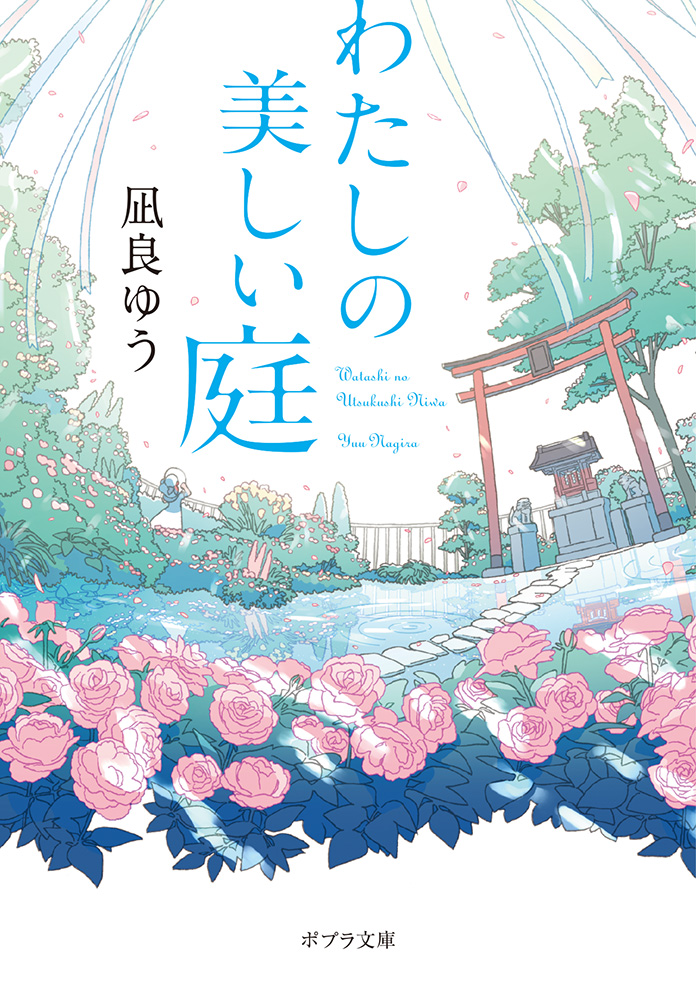
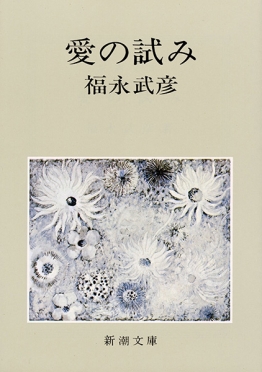
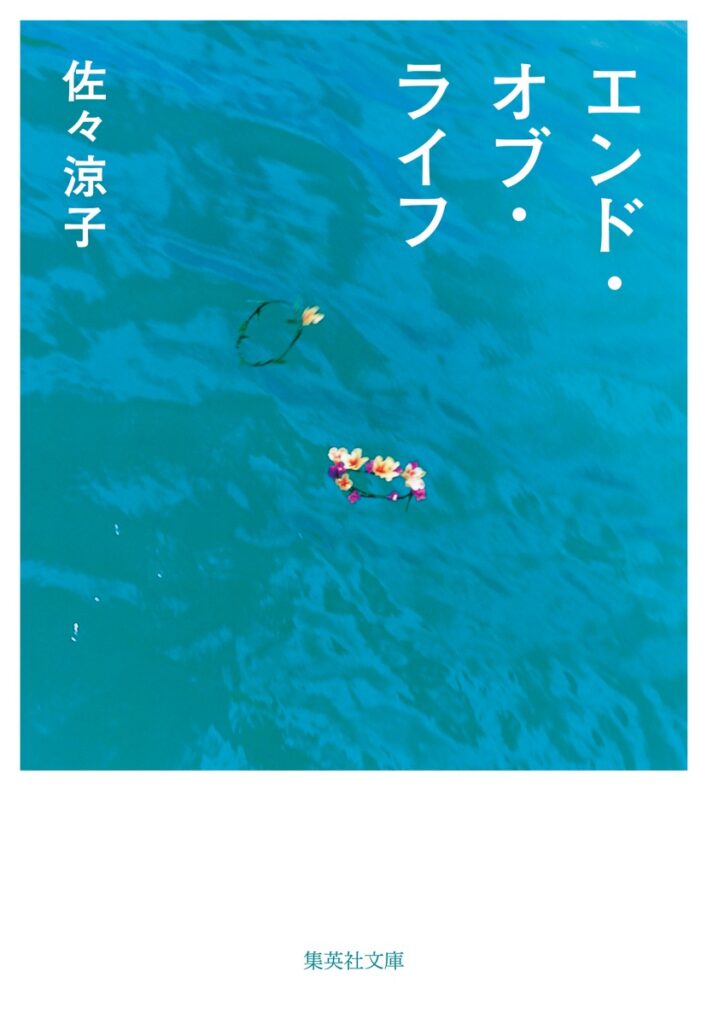
本には読んでいる人の心を揺り動かす力があります。心が揺さぶられたり、思わず涙腺が緩んでしまったり、一生に一度出会えることが奇跡のような本を集めたのが「グッとBook!」レーベルです。
『記憶喪失になったぼくが見た世界』坪倉優介/朝日新聞出版
18歳の美大生が交通事故で記憶喪失になって、それからの人生を綴ったノンフィクションです。映画やマンガである都合のいい記憶喪失ではなくて想像を絶する記憶喪失であることにびっくりします。徐々に周囲を理解して新しい自分を生き始め、草木染の職人として独立するまでの手記はとても心を打ちます。(R.S.)
普通の日常を送っていた18歳の美大生がある日突然交通事故で記憶喪失になる。あたりまえの衣食住の感覚が「無」になってしまった。家族や周囲の暖かい支えのもと「新しい自分」を生き始め独立するまでの感動手記。(T.A.)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『そういうふうにできている』さくらももこ/新潮社
『ぼくは勉強ができない』山田詠美/新潮社
17歳のサッカー好きの高校生時田秀美くんは、勉強はできませんが女性にはもてます。彼は同級生とは異なる価値観を持っていて、それがやや哲学的な感じがします。各章に社会問題や家庭問題などのテーマがあって、主人公がこのテーマとぶつかっていきます。本書を読むと自分が大人になるにつれて周りに同調したり、常識に合わせるようになったりして、なんだかつまらない人間になってしまったなと感じます。(R.S.)
中学生、高校生に読んでもらいたい1冊。人は何の為に勉強をするのか? 勉強ができない人は不幸なのか? ”学校の勉強”とはまた違う視点で人生を考えるきっかけの一冊になると思います。(Y)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『島はぼくらと』辻村深月/講談社
『アスク・ミー・ホワイ』古市憲寿/ 文藝春秋
著者の古市憲寿さんは社会学者で、テレビに解説者として良く出演されています。2018年に初めて発表した『平成くん、さようなら』が第160回芥川賞候補になり、2019年には『百の夜は跳ねて』が第161回芥川賞候補になりました。オランダのアムステルダムに恋人と移住したヤマトは彼女と別れて日本料理店で働いていますが、ある時少し前にスキャンダルで芸能界を引退した俳優の港くんに出会います。本作は古市さんの4作目の小説でロマンチックで幸せな気持ちになれます。(R.S.)
音楽と物語の融合する感覚が魅力。読後、優しい気持ちを誰かに共有したくなるような作品です。(N.S.)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『わたしの美しい庭』凪良ゆう/ポプラ社
『アルマ』J・M・G・ル・クレジオ、中地義和(訳)/作品社
ノーベル賞作家ル・クレジオのルーツであるモーリシャス島を舞台とした物語です。色彩、匂い、温度、喧騒、静けさ、潮の香りなどが手にとってさわれるかのように描写された文章は読み応えがあります。ちなみにモーリシャス島は南半球インド洋にある島国モーリシャス共和国で位置はアフリカ、マダカスカルの東になります。「インド洋の貴婦人」と呼ばれる美しい自然を持ち、多くの観光客が訪れます。オランダ、フランス、イギリスの植民地でしたが1968年に独立しました。(R.S.)
ノーベル賞作家であるル・クレジオは1980年代ごろからモーリシャス島を舞台にした小説を書き続けているが、今作はその最新作である。1年に1度作品を発表するクレジオは、その作風の変化が注目されがちであるが、今作もまた読み応えのある一作である。また訳者はクレジオ研究で名の有名な中地義和で、その正確さと、読みやすさで、信頼度の高い和訳本となっている。(K)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『隔離の島』ジャン=マリ・ギュスターヴ・ル・クレジオ/筑摩書房
『ヘディングはおもに頭で』西崎憲/KADOKAWA
本書の内容から著者の西崎憲さんを若手の作家と思いがちですが、西崎さんは1955年生まれで作曲家、翻訳家、小説家で歌人としても活動されています。大学受験に失敗し、浪人をしながらアルバイトを転々として暮らしている主人公がフットサルと出会います。特に大きな事件が起きるわけでもなく、青年がフットサル、読書会、アルバイトを通して少しづつ自分のことが見えてくるとても日常的な小説です。(R.S.)
大きな事件なんて起こらない浪人生の日常が、こんなにも瑞々しく描かれ、小説となりうるのかと衝撃を受けた一冊。アクエリアスを飲みたくなります。(K)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『百瀬、こっちを向いて。』中田永一/祥伝社
『広い世界と2や8や7』永井祐/左右社
本書はゼロ年代の短歌シーンを代表する歌人永井祐さんの第二歌集です。どこにでもあるような都市の風景、仕事、人間関係。飾らない日常は永井さんによって切り取られ、世界はこんなにも広々と私たちの前に立ち現れます。本の帯に現代短歌を代表する歌人の穂村弘さんの次のようなコメントがあります。「永井祐の登場によって短歌が、目の前の世界の見え方が、変わってしまった。もうもとにはもどれない。なんてことをしてくれるんだ!」(R.S.)
文学と言うと高いハードルを感じる人も少なくないと思いますが、本書を読むと日常の何気ない一瞬の表現、それこそツイートひとつも文学足りえるのではないか?そんな気付きを感じる一冊となってます。(I.A.)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『短歌ください 明日でイエスは2010才篇』穂村弘/KADOKAWA
『わたしの美しい庭』凪良ゆう/ポプラ社
本書は凪良さんが2020年の本屋大賞受賞作の傑作『流浪の月』の次に書かれた作品です。マンションの屋上庭園の奥に神社があり、そこを訪れる生きづらさを抱えた人たちの連作短編集です。凪良さんの小説は読者を今まで読んだことのない世界へ誘(いざな)ってくれます。そして読者は切なく美しく愛おしい物語に出会えたことに感無量となるのです。(R.S.)
私は、「普通」が一番難しいと思う。普通とは、人によって異なる偏った価値観であろう。誰しも、誰かにとって普通じゃない故に傷ついてしまう。そんな時、足元に目を落とす前に、是非この本に目を落としてほしい。(K.Y.)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『流浪の月』凪良ゆう/東京創元社
『愛の試み』福永武彦/新潮社
本書はいくつかのエッセイと小説という構成を繰り返して「愛」への考察を深めていきます。愛を得ることで孤独が薄れたり、愛を失うことで孤独が深まったりするのではなく、孤独は常に自分の中にあって孤独との向き合い方を考えさせられます。(R.S.)
学生時代に失恋した頃、先輩にすすめられて読んで、立ち直れたような記憶があります。愛って本当にむずかしい。愛ってなんでしょうね。(T.N)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『砂の女』安部公房/新潮社
『エンド・オブ・ライフ』佐々涼子/集英社
本書は在宅・終末期医療のドキュメントで第3回『Yahoo!ニュース本屋大賞 2020年ノンフィクション本大賞』を受賞しています。著者の佐々涼子さんはノンフィクション作家で『エンジェルフライト』で第10回開高健ノンフィクション賞を受賞して、その後『紙つなげ』などの著作があります。誰にでも訪れる、いつか自分にもやってくる内容にとても考えさせられます。(R.S.)
「死」に直面して、人は「どのように生きるのか」。周囲はどのように支えるのか。著者の母や友人の看護師等の実体験をもとに「在宅医療」というテーマでより納得できる終末医療の在り方を考えさせてくれるノンフョクションです。(H.F.)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『死すべき定め』アトゥ-ル・ガワンデ/みすず書房
『ツナグ』辻村深月/新潮社
一生に一度だけ死者との再会を叶えてくれるという「使者ツナグ」の5話からなる連作短編集です。ツナグの依頼者は心に痛みを抱えていますが、死者と一夜だけ出会うことにより自分と向き合いそして未来へ進んでいきます。丁寧でわかりやすい描写で引き込まれ、読後感も良く人に薦めたくなります。2012年に映画化もされました。(R.S.)
死んだ人の想い。遺された人の想いという2つの想いがめぐりあい、すれ違うさまとそれを乗り越え未来に向かう姿に感動を覚えます。(K.D)
■こちらの本をご覧になった方へのおすすめ
『凍りのくじら』辻村深月/講談社
2025年9月24日 更新